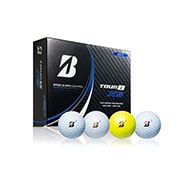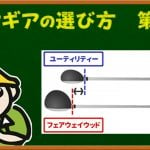練習で一番地味で飽きやすく、一番なおざりにされがちなのがパターです。この地味な練習を自宅でラウンド前だけでなく日々精進して頂きたいものです。
地味な練習ほど楽しむ工夫が必要で、忍耐力が試されます。主に自宅ではロングパットの練習環境を作り出すのは難しいですが、ショートパットならパターマット1枚で様々な練習ができます。カップイン率を上げる為だけが練習ではありません。基礎レベルを底上げし、ラウンドに役立つ日頃の練習方法をご紹介します。
目次
ショートパットを練習する上での確認事項
まずは確認事項を5つ覚えておきましょう。
左右片手でのストローク
これはパターだけでなくアプローチでも用いられる練習ドリルです。
パターでの目的は左右同じ力でグリップし、手首を使わずショルダーストロークができているかを確認する事ができます。
どちらかの力が強すぎたり、手首(スナップ)の強弱で距離感を作ろうとする悪い癖の矯正にもなります。片手でフェイス面がブレないでストロークすればパターでも真っすぐな転がりが身に付きます。松山英樹選手も積極的に取り入れている練習です。
フォロースルー押し込みドリル
これも代表的な練習です。通常はアドレスが終わってバックスイングをする訳ですが、この練習はバックスイングを行いません。
アドレスの状態からボールをフェイス面でフォローへ押し出す様に真っすぐ長くボールを転がすトレーニングです。これの目的はインパクトで緩ませない事です。特にショートパットではインパクトの瞬間に力の強弱を調整してしまう方が多いのですが、このドリルを行う事でインパクトでの緩みや極端に力を加えるなどの不自然さが解消されてきます。
更に、インパクトが緩まなければより小さい振り幅で長くボールを転がせるようになります。ラウンドの当日、練習グリーンでも積極的に行い普段いかに大振りしすぎてインパクトで調整しているかが把握できるでしょう。
ただし、このバックスイングを取らないストロークはルール違反ですので、ラウンド中は行わない様に注意しましょう。
できるだけ小さい目標へ転がし当てられるように
カップの直径はおおよそ11㎝です。信じられないかもしれませんが、一升瓶がスッポリと入ってしまうほどの大きさです。その昔、一升瓶を寝かせて、底をカップ代わりに見立てて練習を行ったことが懐かしく思います。
普段からカップと同じ大きさで練習するのも良いのですが、先に紹介したカップを1円玉に置き換えてみたり、もっと直径の小さい目印を作ってカップに見立てたり、日頃からカップより小さい目標で練習しておくと実際のカップが大きく感じるようになり、精神的にも楽になるでしょう、更に正確に目標へフェイス面を向ける練習にもなるのでやりがいがあるドリルです。
もっと自分に合うグリップ方法が無いか確かめてみる
パターのグリップは、他のクラブに比べて丸みの少ないのが特徴です。いわば「面」が存在するかのようなグリップ形状です。この形状は左右均等に力が保ちやすく、面がブレにくくなります。
最近ではかなり特徴的なグリップ方法が目立つ様になってきました。今の慣れ親しんだ握り方でも良いかもしれませんが、ひょっとしたら握り方を変えるだけでもっと劇的にパットが良くなる可能性が有るかもしれません。各々の特徴などここでは省きますが、どの様な握り方が有るのかご紹介します。
①逆オーバーラッピンググリップ
②クロスハンドグリップ
③スプリットグリップ
④クローグリップ
⑤アームロック式グリップ
⑥プレイヤーグリップ
それぞれを実際に試してみましょう。新たな発見やしっくりくるグリップと出会えるかもしれません。
同じ傾斜度でもスライスの方が大きく曲がる
フック、スライス、同じ傾斜度でストロークした場合はスライスの方が曲がり度合いが大きくなるのをご存じでしょうか?
それはパターのロフト角に関係してきます。通常のショットで爪先下がりを思い出してください。この傾斜ではクラブが長くなるほどスライス度合いが大きくなります。これはクラブのロフトが少なくなるほど右を向いてインパクトしやすくなるからです。
同じことがスライスラインのパッティングでも起こります。パターのロフトは一番少なく、スライスラインは基本的に爪先下がりからのパッティングなります。例えばカップ2つ分スライスと読んだ場合は、カップ2つ半や3つ分と、やや厚めにラインを決定する様に意識しましょう。
たとえ外れてもプロラインで外れるので大きくオーバーする事は少なくなります。3パットで多く見られる組み合わせは、下り+ロングパット+スライスラインです。このラインの時は充分に注意が必要です。
パター自体の重量
ここも非常に重要なポイントです。最初に市販されている状態は比較的ヘッドの重量が軽い事が多いです。グリップは標準で太い形状が挿してあるのですがヘッドが軽いのは不釣り合いです。最近流行りの柔らかく太いグリップは重量が有るので、その分ヘッドにも重量を加えないとボールの勢いが弱い貧弱な転がりになってしまいます。
理想はヘッドの方が重くなっている事です。重ければその分だけ小さい振り幅で長く転がってくれます。「重いグリップ交換=ヘッドも重く」を忘れずに。普段からショートパットで打ち切れない方は、ヘッドに鉛を貼って、8g~10g程度重くするだけでボールの転がりが変わってくるのが分かると思います。届かなかったショートパットがカップまで届くようになり、カップイン率UPに希望が持てます。
簡易的メジャーを作成しよう
市販されているメジャーは距離も短く、持ち運びにも重く、パター練習には不向きです。そこで自作のメジャーを作成する事を強く勧めます。幅3~5㎝で長さ5メートルの布製メジャーを作りましょう。1ヤード毎(約91㎝)に印を付けておき、1ヤード毎の細かな距離感練習ができ、感覚を養いやすくなります。
ラウンドの当日であれば練習グリーンにメジャーを置いて、より正確なタッチの練習が行えるでしょう。更にこのメジャー練習を行う事で、他のコースとの転がりの違いも把握できます。ショートパットは感覚よりも技術です。1ストロークでも少ないに越したことはありません。
グリーン外からも距離感を出せる様に
これも時間を掛けて覚えていく事になりますが、グリーンの外からもパターの練習を行いましょう。近くの花道からやちょっとしたラフから、極端ですが、平地でフェアウェイなら30ヤード手前から転がり寄せるのも良いでしょう。
海外(特にヨーロッパ)のコースでは風の影響が強く、低く転がす地上戦が多く見られます。日本ではとりわけウェッジで寄せて1パットの様な綺麗なゴルフが求められがちですが、海外選手は転がす技術もかなり高いです。育ったコース環境もありますが、転がす事のイマジネーションに長けています。普段のラウンドで競技とかでなければ、もっと遠い所からパターを積極的に活用してみましょう。グリーン廻りでアプローチが苦手な方は必ず取り入れて損はないでしょう。
ただし、実際に活用するには事前の練習が必要です。フェアウェイといってもグリーンよりは芝の抵抗が多く、同じ5ヤードでも振り幅はかなり変わってきます。様々な箇所からパターが使える様になれば3パットの数も自ずと減ってくる事でしょう。
まとめ
パターは一番地味な1打ですが一番重要な1打でもあります。300ヤードのショットも30cmのパッティングでも価値は同じ1打です。ドライバーショットとパターのストローク、どちらが多いかは言うまでもありません。
その地味なパターを得意とするには日頃の様々な練習が重要となります。工夫次第でとても楽しめるパター練習です。どの様な練習が自分にとって長時間楽しめるのかを考えるのも上達には必要です。
構え方・打ち方など技術的な事ももちろん大切ですが、もっともっとパターを多く活用する時間や回数を増やしましょう。細かい事を考えずともいつの間にか距離感のイメージやロングパットのタッチが合ってきます。練習の楽しさが見いだせれば練習時間が勝手に増え、どんどん上達していく事でしょう。