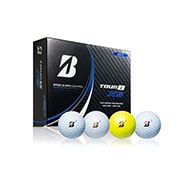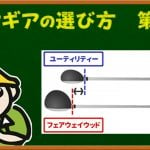ゴルフに限らず、スポーツであれば好調不調は常に繰り返しです。特に初級者となれば基本がままならないため、調子の良し悪しの影響が大きいのは必然でしょう。
そしてそのブレを減らすためには基本の練習が何よりも重要です。基礎はプロやアマチュア、男性女性、大人子供に関係なく万人に共通する事。ゴルフにおいては、調子が悪ければどうしてもクラブの動きや身体の動き(動いているもの)に意識が飛びがちですが、もっと当たり前の事に意識を向けてみることも重要です。
そこで今回は、ハーフショットでゴルフスイングの基本を身につけることを目標に基礎固めの方法などを解説していきます。
目次
基礎固めの前に重要な事

基礎を固める前にゴルフのスイングにおいて、もっとも重要な前提の確認をしましょう。
動かない箇所のチェック
まずは下記の3点を中心に動かない場所、動きの悪い箇所の再チェックを行います。
動かない箇所①
グリップが正しく握れているか。いつも同じに握っているつもりでも徐々にズレが生じ、気づきにくい箇所です。特にスイング中はフェイス面の向きに大きく影響するので毎回正確に握る癖を付けたいものです。
動かない箇所②
ボールとの距離・位置。これも毎回ズレている方が目立ちます。プロや上級者でさえアライメントスティックなどを利用して毎回目標へ正しくスタンスしているかをチェックしています。
一方、初心者は打つ、当てる事に意識が多く働くのでスイング中ともなるとこのボールポジションへの意識はほぼゼロに近いでしょう。
動かない箇所③
アドレスの向きやポスチャー(姿勢)。向きに関しては先述のアライメントスティックでおおよそ自己確認が可能です。但し、飛球線に対して5線(爪先、両膝、腰、肩、両肘)が平行になっているかを確認するのは動画や鏡を使わないと難しい部分です。
特にスライスに悩まれている方は飛球線に対して両肩が左向きになっていることが多いのでチェックしましょう。
継続は力なり
「何か新しい動きを付け加えたい」または「余計な動きを取り除きたい」と思った時、自分に合ったドリルをいくつ持ち合わせているかがポイントとなります。
同じ結果を得ようとした時でもイメージがピンとくるドリル、全くイメージが出ないドリルと色々あるものです。自分に合うドリルを調子の悪い時だけ行うのではなく、常に日々のルーティンとして取り入れながら練習しましょう。
よくゴルフレッスンなどでは「制限と解放」という言葉を使いますが、これはドリルの時間をいつもより長く用意し、その後いつも通りにショットを行う一連の流れの中で感覚の変化を掴んでもらうための手法です。制限(ドリル)より解放(いつものスイング)の時間が多いとスイングを変化させるのは難しいと言われます。
トッププロが画面の向こう側で簡単にナイスショットを打っていますが、あの状態になるまでどれだけの時間を使っているかを想像してください。上級者ほど自分のドリルを持っているのです。
どのクラブでどの様なミスが発生しやすいかを明確にし、クラブ選択に余裕を持たせる
クラブ毎にもミスのパターンが存在します。基本から改めて確認しておきましょう。
ミスの種類を考える
長いクラブはチョロが多い、短いクラブはダフリが多いなど、どのクラブでどの様なミスが出るのか統計を出してみましょう。後述するハーフスイングでクラブごとに意識する部分が変わってきます。このミスを事前に知っているのと知らないのでは改善効率が雲泥の差となります。
クラブ毎の飛び方も知っておこう
長いクラブは左から右へのスライス、短いクラブは左に一直線…などこの場合は同じ理由によってミスが発生していますが、中にはクラブが変わるとスイング軌道も変わってしまう方も多く見受けられます。ボールフライトをきちんと把握する事でハーフショットでの練習がより濃いものになります。
ハーフショットはラウンドでも様々な状況に対応できる
特にアイアンなどは、毎回自分のフルスイングで対応できるピッタリの距離が残る訳ではありません。7番じゃ届かない、6番じゃ大きいなどのケースが考えられます。こんな時にハーフショットができる方とできない方では気持ちに大きな差が出てきます。
ハーフショットが出来ない場合には、短いクラブで思いっきり打って届かせようとする選択をする方が多いですが、これはとても危険です。
対して長いクラブで「飛ばさないハーフショット」が出来れば気持ちにもスイングにも余裕が生まれ、良い結果が出やすくなります。更に向かい風の時や打ち下ろしの場面でも役立ち、もっとゴルフを楽しめます。
ハーフショットのスイングで意識する事

それでは今回の本題のハーフショットについてここから解説していきましょう。
何のためのハーフショットなのか
まず改めて何を目的としてハーフショットを行うのかを確認しましょう。腰の高さから反対の腰の高さまでのエリアを「ビジネスゾーン」。人によっては時計の「9時~3時の範囲」と表現する場合もあります。どちらの表現も同じ意味合いなのでどちらで覚えても差し支えありません。
このエリアでクラブが複雑な動きをしていたり、フェイス面の向きが左右にブレていたりするので球筋が安定しない状態が発生してしまいます。そこで、このハーフスイングを行う事で動きのエラーを修正するのが目的です。
各クラブで「アドレスは正確か」「軌道は適正か」「フェイス面の向きが適正か」「前傾角度がキープされているか」「しっかりと左足重心でインパクトを迎えているか」など課題が盛り沢山です。
ハーフショットは一見地味ですが、人それぞれ意識する部分が異なるので何を意識するのかをしっかり1球毎に確認する癖を付けましょう。
飛ばそうとしない
ハーフショットでも力一杯のスイングを目にします。これでは自分のエラーを矯正する事になりません。力一杯フルスピードで打っていても動きが感じられないので、無駄になってしまいます。
こんな時におすすめの方法は半分程度のスピードで反復する事です。徐々に自分の動きやクラブの動きなどが感じ取れるようになります。ラウンド中、フルスピードでフルスイングして動きを感じることは少ないでしょう。恐らく、打った打球を基準に判断をしているはずです。
ナイスショットであれば100%正しいスイングだったとなりがちですが、スイングを後から分析すると自分の動きはあまり理解できておらず、再現性がない場合も多くあります。
ゆっくり反復することで自分のエラーを直すことができますし、全てのクラブが同じ意識で扱えたら基本レベルが確実に上がったと認識できるでしょう。
全てのクラブで練習する
ドライバーは調子がいい、アイアンが調子悪い、またはその逆。これもゴルフあるあるですよね。どのクラブでも意識は同じ、同じ扱い方です。できる限りバラつきを無くすためにもドライバーでもフェアウェイウッドでもユーティリティーでもハーフスイングで練習してみて下さい。
特に陥りやすいのはアイアンをドライバーと同じスイングの大きさ、同じスピードで打ってしまうエラーです。アイアンの目的は主にグリーンに乗せる事、ピンを狙う事であって決して過程は評価されません。
150ヤードを9番で打とうがPWで打とうが、グリーンに乗らなければ意味がありません。全ての距離に全てフルスイングでのクラブ選択ではゴルフの幅も広がらず、レベルUPも難しいでしょう。アイアンの役目を理解し、コントロールショットを磨いて技を多く持ち、ゴルフに幅を持たせましょう。
まとめ
ここ近年、「ハーフスイング」や「ハーフショット」という言葉がゴルフ業界でもかなり定着してきました。色々な理論メソッドやドリルがある中でこれほど多くのプロや指導者が「ハーフスイング」「ハーフショット」と口にするのはやはり効果が高いからでしょう。
それなりの技量ならもっと複雑で特殊な練習も取り入れたりしますが、初級者から上級者、またはプロまで万人に共通する練習手段は多くありません。これほど多くのレベルのゴルファーに共通して行える方法は少ないでしょう。
ハーフと言えども、スイングの8割がここに集約されています。各クラブ、同じ動き、同じタイミングで扱えるように反復し、調子の悪い時だけでなく、良い時も悪い時も常に取り入れて不調からの脱却や基礎レベルUPに繋げましょう。